※本ページはプロモーションが含まれています

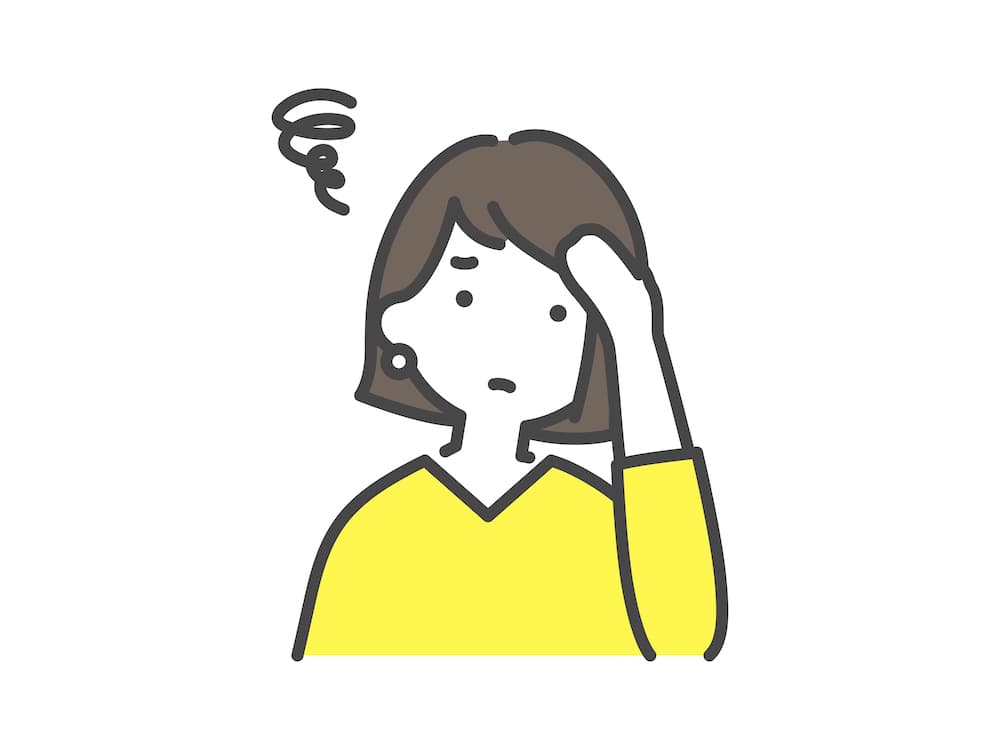
今回は、このような疑問にお答えします。
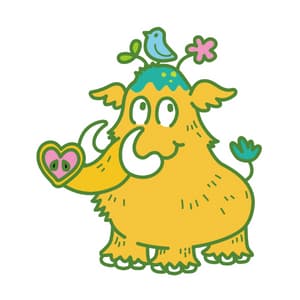
カブトムシの幼虫の飼育は、自然の力を間近で体験する素晴らしい機会です。しかし、初心者にとっては、どのようにして健康的に、そして可能な限り大きなカブトムシに育て上げるかが一つの挑戦となります。
この記事は、そのような初心者の方々に向けて書いたガイドです。
カブトムシの幼虫の基本情報から始まり、飼育に必要な準備、飼い方のポイント、健康管理、そして成虫への成長過程までを紹介しています。手に入れた幼虫を丁寧に育て、見事な成虫へと成長させるために必要な知識を一緒に学びましょう。
まだカブトムシの幼虫を手に入れていない方は、当宿の宿泊プランをご利用ください。カブトムシの幼虫と簡易飼育セットが付いた宿泊プランをご提供しています。
カブトムシの幼虫を手に入れて飼育をはじめたい方は「森でカブトムシの幼虫採集プラン(簡易飼育セット付き)」をご利用ください!
京阪神以外にお住まいの方は、全国のカブトムシが捕れる宿泊施設をまとめた以下の記事をご覧ください。
それでは、どうぞ!
カブトムシ幼虫の基礎知識

カブトムシは、日本をはじめとするアジア地域に広く分布しており、特に子供たちに人気のある昆虫です。幼虫期間は卵から孵化する8月上旬からサナギになる前の5〜6月までの10ヶ月ほどとされています。
カブトムシの幼虫は、その大部分を土中で過ごし、主に腐葉土を食べて成長します。幼虫は非常にデリケートで、特に温度と湿度の変化に敏感です。そのため、飼育環境の管理が重要になります。
カブトムシの幼虫は体色が白く、C字型の体をしており、大きさは種類によって異なりますが、一般的には80mm〜120mmの間で成長します。幼虫の期間中、脱皮を繰り返して1令幼虫→2令幼虫→3令幼虫へと成長します。
カブトムシの孵化(1令幼虫へ)
カブトムシの産卵後、2週間ほどすると、メスが産んだ卵が割れて中から幼虫が出てきます。
これを孵化(ふか)と呼びます。産まれたばかりのカブトムシの幼虫は、初令幼虫(しょれいようちゅう)または1令幼虫(いちれいようちゅう)と呼ばれます。初令幼虫の体長は約8〜10mmほどです。
カブトムシ1回目の脱皮(2令幼虫へ)
カブトムシの1令幼虫は、1週間ほどで自らの皮膚を脱ぎます。この現象を脱皮(だっぴ)と呼び、この後の幼虫を2令幼虫と言います。
体には、たくさんの細かい毛があり、周囲の状況を感じ取っています。
カブトムシ2回目の脱皮(3令幼虫へ)
2令幼虫は3週間ほどで2度目の脱皮を行います。この後の幼虫を3令幼虫と呼び、初期の体長は約40mmほどです。3令幼虫は、自身の大きなアゴを使いながら腐葉土などをたくさん食べて成長します。体長は8~12cmにまで成長します。
カブトムシ幼虫の飼育準備
カブトムシ幼虫の飼育に必要なアイテム一覧
カブトムシの幼虫飼育に必要なものは以下の3つです。
全てホームセンターやネット通販で手軽に入手できます。参考までにネット通販で買えるカブトムシ幼虫の飼育用品も紹介します。
- 飼育ケース
- 幼虫フード(マット)
- 昆虫ウォーター(栄養保水液)
飼育ケースは、できれば1匹ずつ単体飼育するのがオススメですが、4匹までは小、8匹までは中、8匹以上は大をオススメする人もいます。価格は1,000円〜。2Lペットボトルで代用可。
幼虫フード(マット)は、600円/10Lで購入できます。成虫用のマットでは栄養が不足してしまうことがあるので幼虫専用または幼虫と成虫の両方に使えるマットを選びましょう。
以下で紹介するものは幼虫・成虫の両方に使えるタイプです。
昆虫ウォーター(栄養保水液)は、500円/250mlほどで購入できます。なくてもOKです。水や幼虫フード(マット)で代用可。
カブトムシ幼虫のオス・メス見分け方
カブトムシの幼虫は、オスとメスの間に明確な外見上の違いはほとんどなく性別を区別することが非常に困難です。しかし、3令幼虫まで育った段階では幼虫のお腹側、特にお尻の近くにある特定の模様を見ることでわかることがあります。
オスの場合、お尻から2番目と3番目の線の間にVの印があることが特徴です。一方、メスにはこのような印はありません。
またメスの幼虫のおしりを見ることでわかる場合もあります。おしりに白い点が浮き出ているとメスの可能性があります。
カブトムシ幼虫の飼育スタート

カブトムシ幼虫の飼育セット組み立て方
- 飼育ケースに10センチほど幼虫フード(マット)を入れる
- 幼虫フード(マット)の水分量を調整する
カブトムシ幼虫の飼育セットはとてもシンプルです。飼育ケースに幼虫フード(マット)を10センチほど入れてカブトムシの幼虫を入れます。
幼虫フード(マット)の水分量は、手で握った時にそのまま形が崩れない状態になるくらいです。ほとんどの場合、購入した幼虫フード(マット)は適切な水分量が保たれているのでそのまま使えます。
飼育する中で土の表面が乾燥してきたら霧吹きで水をかけ適切な水分量を維持しましょう。
カブトムシ幼虫の入れ方と注意点
幼虫を飼育ケースに入れる際には、以下の点に注意してください。
- 慎重な取り扱い:幼虫はデリケートなので、優しく丁寧に扱います。手で直接触れる場合は、手を清潔にしてから行いましょう。
- 一匹ずつ入れる:幼虫をケースに入れる際は、1ケース一匹ずつが理想です。これにより、幼虫同士のストレスを最小限に抑えることができます。
- 幼虫の配置:幼虫をマットの表面に置き、自然に土の中に潜るのを待ちます。強制的に土に埋めるのは避けましょう。
- 飼育環境の確認:幼虫を入れた後、ケース内の温度と湿度を再度確認し、適切な状態に保ちます。必要に応じて、マットの湿度を調整するために水をスプレーすることがありますが、過剰な水分は避けましょう。
- 観察と環境管理:幼虫を入れた後、定期的に飼育環境を観察し、必要に応じて温度や湿度を調整します。特に夏場や冬場は室温が大きく変動するため、注意が必要です。
- ストレスの軽減:幼虫はストレスに敏感なため、飼育ケースの移動や不必要な観察は控えめにし、静かな環境を提供します。
国産のカブトムシは日本の四季に適応した虫ですので、35℃を越えたり氷点下になるような気温を避ければ大丈夫だと言われています。室内(自宅の玄関)で常温飼育すればOK!
カブトムシ幼虫の飼育ポイント
以下にカブトムシ幼虫の成長過程ごとの飼育方法を紹介します。
カブトムシの孵化(1令幼虫へ)
カブトムシの産卵後、2週間ほどすると、メスが産んだ卵が割れて中から幼虫が出てきます。
これを孵化(ふか)と呼びます。産まれたばかりのカブトムシの幼虫は、初令幼虫(しょれいようちゅう)または1令幼虫(いちれいようちゅう)と呼ばれます。初令幼虫の体長は約8〜10mmほどです。
カブトムシ1回目の脱皮(2令幼虫へ)
カブトムシの1令幼虫は、1週間ほどで自らの皮膚を脱ぎます。この現象を脱皮(だっぴ)と呼び、この後の幼虫を2令幼虫と言います。
体には、たくさんの細かい毛があり、周囲の状況を感じ取っています。
カブトムシ2回目の脱皮(3令幼虫へ)
2令幼虫は3週間ほどで2度目の脱皮を行います。この後の幼虫を3令幼虫と呼び、初期の体長は約40mmほどです。
3令幼虫は、自身の大きなアゴを使いながら腐葉土などをたくさん食べて成長します。体長は8~12cmにまで成長します。
1匹の幼虫は、成虫に成長するまでに3リットルの腐葉土を食べると言われています。大きなカブトムシを育てたい場合は、特に3令幼虫の時期にエサを切らさず、快適な飼育環境を用意することが重要になるでしょう。
カブトムシ幼虫の日々の管理
カブトムシ幼虫の健康チェックポイント
カブトムシの幼虫を健康に育てるためには、定期的なチェックが不可欠です。以下は幼虫の健康状態を確認する際の主なチェックポイントです。
- 活動性と挙動:元気で活発な幼虫は健康の良い兆候です。無活動状態や異常な動きは注意が必要です。
- 体色と形状:健康な幼虫は一般的に均一な白色をしており、体形はC字型です。異常な色や腫れなどがあれば注意が必要です。
- 食欲:健康な幼虫は良好な食欲を持ちます。食べなくなった場合は、環境や餌に問題がある可能性があります。
- 排泄物:排泄物の量や状態は、幼虫の健康状態の良い指標です。異常が見られる場合は環境の見直しが必要です。
カブトムシ幼虫の一般的な病気と対策
カブトムシの幼虫は、特に湿度や衛生状態の管理が不適切な場合、いくつかの病気にかかりやすいです。以下は幼虫がよく経験する一般的な病気とその対策です。
- カビ病:過湿状態で発生しやすいです。幼虫の体に白いカビが生えるのが特徴です。対策としては、湿度の適切な管理と定期的なマットの交換が重要です。
- ダニの被害:ダニは汚れたマットや高湿度の環境で繁殖します。ダニによる幼虫の健康被害を防ぐためには、マットの清潔さを保ち、定期的な交換を行うことが重要です。
- ブヨブヨ病:幼虫が異常に膨れ上がる病気で、不適切な餌や水分過多が原因で起こります。バランスの取れた餌やりと適切な水分管理が予防につながります。
これらの健康管理のポイントに注意を払い、適切な飼育環境を維持することで、カブトムシの幼虫は健康的に成長し、美しい成虫になる可能性が高まります。日々の観察とケアが、幼虫の健康を守る鍵となります。
カブトムシ成虫への成長
カブトムシ幼虫から成虫への変化
カブトムシの幼虫が成虫へと変化する過程は、お子様にとって自然界の不思議を体験するチャンスです。この変化は以下のステップで進みます。
- 蛹化の兆候:5月末〜6月上旬に近づくと、幼虫は活動を減らし、食欲が落ちます。これは蛹化の準備が始まっている兆候です。
- 蛹への変態:幼虫は土中に潜り、蛹室を作ります。その後、体が硬化し蛹へと変態します。この過程で、外見は完全に変わります。
- 成虫への変化:蛹の状態で数週間を過ごした後、カブトムシは成虫として蛹室から姿を現します。最初は柔らかく色も薄いですが、時間とともに体が硬化し、典型的な黒い色になります。
カブトムシの成虫になった後の飼い方
成虫になったカブトムシへの適切なケアは、その寿命を延ばし健康を保つために重要です。
- 適切な飼育環境:成虫は幼虫と異なり、より広い空間と登るための枝や木を好みます。飼育ケースは成虫のサイズに合わせて適切な大きさであることが大切です。
- 餌の提供:成虫は果物や昆虫用ゼリーなどを食べます。新鮮な餌を定期的に提供し、水分補給も忘れないようにしましょう。
- 清掃と環境の管理:成虫も清潔な環境で過ごすことが重要です。定期的にケースを清掃し、適切な温度と湿度を保つことが必要です。
- 観察とケア:成虫も日々の観察が重要です。
カブトムシの成虫の飼い方についてはまた別の記事で詳しく紹介します。
以上が、カブトムシ幼虫の飼い方です。
当宿ではお子様が興味を持ったときに、いつでもカブトムシの飼育がはじめれる宿泊プランをご用意しています。気になる方はぜひ淡路島マンモスのホームページをご覧ください。
それでは、また!





